feature
特集
21.12.21
「さどの島銀河芸術2021」AFTER TALK Interview with Noi Sawaragi × Morito Yoshida
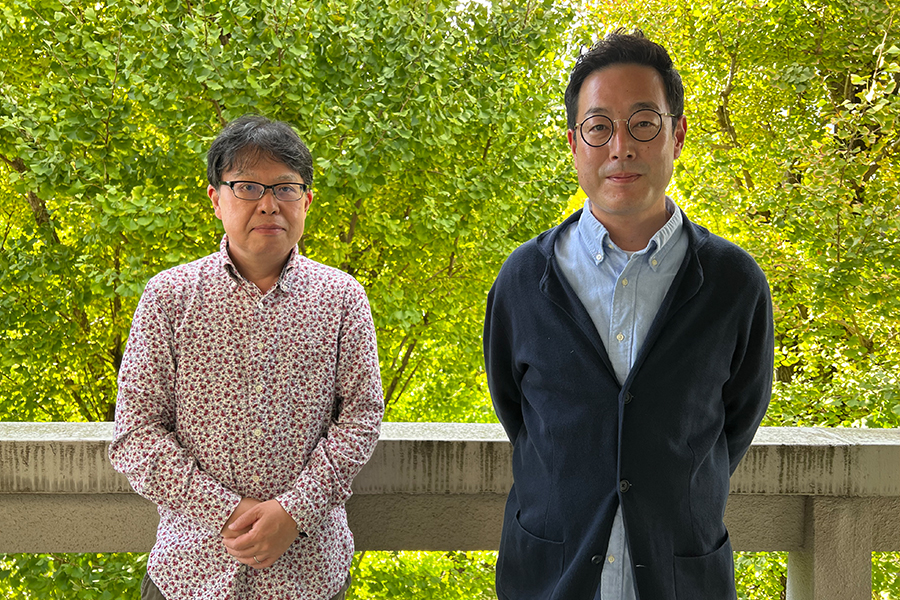
2021年8月8日からスタートし、11月7日に幕を閉じた「さどの島銀河芸術2021」。2016年から毎年開催するアートプロジェクトの本祭としては第一回目を終え、本芸術祭のアドバイザーの一人で、美術批評家の椹木野衣さんと、芸術祭の発起人であり、総合プロデューサーでアーティストの吉田モリトさんが、プロジェクトの始まりから、佐渡という土地の可能性、今後の展望を語り合う。
自然発生的に始まった、佐渡発の芸術祭
椹木野衣(以下、椹木):そもそも佐渡で芸術祭をやろうという話は居酒屋で生まれたんです。行政が主導して運営している芸術祭が多い中、本当に手弁当でやろうと。
吉田モリト(以下、吉田):2015年の第2回の水と土の芸術祭に一緒に行きませんかと椹木さんにお誘いいただいて、それで総合ディレクターの小川弘幸さんと、当時新潟在住だった岡本太郎研究者の貝瀬千里さんと4名で作品を巡ったんですよね。その後に懇親会みたいな形で居酒屋に行って。
椹木:きっかけは僕が、2015年に、それまではあまり縁がなかった新潟に頻繁に行くようになった。新潟に呼ばれていた感じ。新潟には何度か行ったことがあったけれど、どんな土地なのかという視点では見たことはなくて。新潟市で行われた水と土の芸術祭は、潟というテーマだったのですが、作品を見て巡っていたら、大きな潟が随所にあって。今は埋められてしまっていても、潟の文化が根付いていた場所なのだとわかった。
吉田:そうでしたね。
椹木:そもそもなぜ潟があるかというと、かなりの部分が湿地だからですよね。相当な苦労があって土壌改良をし、そこから米どころにまでなった。けれど毎日何百トンという水を排水しないと水浸しになってしまう。新しい潟っていうのはそういうこととも繋がりがある名前であると知った。それは新潟市を訪れたときの話ですが、佐渡という離島まで含む幅がある新潟は、実は地域によってかなり特性が違うすごく多様性のある県なんだと各地を巡ってわかった。土地ごとの特性や地理的なあり方によって、芸術祭も違った可能性が出てくるなと感じているところに、モリト君から佐渡で芸術祭をやろうと思っているという話が来たんです。
吉田:2016年にまずはやってみようと芸術祭を始めましたが、助成金をもらったり、形としてきちんと作り上げていくためにアドバイザーが必要ではないかと思い、まずはじめに椹木さんにお声かけさせていただいて、その後、小川弘幸さん、2018年には、宇川直宏さんにもお願いしました。以前から椹木さんには、「佐渡にぜひ来てください」とはお声かけしていたんですよね。
椹木:離島で新潟県の中でも距離があるから行ったことはなかったけれど、行ってみたら佐渡ならではの地理、歴史、文化があると知って、積極的に関わりたいなと思うようになったんです。
吉田:きっかけはよくある過疎化で元気がなくなった地域をアートの力で何とかできないかという思いから芸術祭を始めたものの、やったこともないし、どうしていいか全くわからない状態だったので。椹木さんにはキュレーション以前の、もっと全体的な、大きな動き、ビジョンを相談させていただきました。
椹木:現在各地に広まった芸術祭は北川フラムさんが作り上げたフォーマットで、越後妻有の大地の芸術祭(2000年~)と、瀬戸内国際芸術祭(2010年~)が成功モデルとなったのは、大地は里山、瀬戸内は内海が元々文化の発信拠点だったことを振り返る姿勢があったから。でも振り返るときには必ず負の遺産があって、誰も見向きもしないようなそんな部分をアートで掘り起こすという視点が世界的な発信力に繋がったんです。佐渡の芸術祭に関わるのならば、負の遺産も含めて記憶を継承しながら古いものも含めて新しいアートとして表現していかないと、と思った。さどの島銀河芸術祭という名前も、モリトさんたちに聞くとなぜ銀河なのかという答えがあまり出てなくて。それで、なぜ佐渡で銀河なのかという明確な理由を考えて言葉に落とし込んだほうがいいとアドバイスしたり。佐渡の芸術祭という根っこみたいなものをきちんと確かめておかないと、ただの街おこしになってしまう。佐渡はどういう場所なのかをもう一度考える機会にならないと意味がないので。
吉田:やればやるほど問題が、根っこが深いんですよね。毎年勉強している最中ですが、だんだんとそれがわかってきました。
椹木:負の遺産をないことにするのがこれまでの地域おこしのやり方だけれど、規模は違ってもそういうものは近代化の中で必ず発生していると思う。同じことが個人個人にも言えて、近代の生活を享受するうえで個人個人も何らかの形で傷ついているんじゃないかな。だから土地のことだけれど自分のことでもあって、それを隠して暮らしていても根本的には解決しない。大変なことかもしれないけれど、そういうアートを通して自分の来歴をもう一度見つめ直すきっかけになるし、勇気をもらえる。芸術はそこに焦点を当てないとエンターテインメント何が違うの?という話になってしまうから。

コロナ禍で開催した2021年の本祭
吉田:今年「さどの島銀河芸術祭2021」としてようやく本祭を開催しましたが、まだまだ成長途中と言いますか、ようやく芽が出てきたところなのかなと。どういう芸術祭にしていこうかというビジョンについては、もうちょっと具体的に再構築していかないといけないと思っています。
椹木:途中でコロナ禍になったのはすごく大きいですよね。そうじゃなかったらまた違う展開もあったのではないかと。例えば、コロナの影響で中止になったり、延期になったり、規模の大きな芸術祭が大変な思いをして何とか持続している状況で、体制としても小さい佐渡が、どうやって続けていけばいいのか難しくなったところはあったと思う。そんな中、全員がPCR検査をしての催しへの参加だったり、試行錯誤を経て開催に至っているので、本祭はそういうある意味トレーニングが終わった時点として、やれることはやれたかなと思います。でも十分に展開できたわけじゃないから、それを今後に繋げていけばいいのかなと。
吉田:今年も本祭なのにコロナの影響があって、何度も市と協議しました。市としてはやってほしい、けれど、島民からは母も含めて批判もある中で、スタートして一人でも感染者が出たら終わってしまうと思ったので、当たり前ですが、PCR検査も含め関係者の感染拡大防止対策を徹底したり、参加アーティストが海外から来日する際の隔離期間の調整だったりと難しい面はありましたが、一番大変だったのは集客の面でした。公に来てくださいと言えないのが辛かったですね。ただ、人数を限定してですがキャンプフェス「FRACTAL CAMP」を実施できたことは、今後の礎になったかなと。
椹木:一方で発見もあって、SADOMMUNEのプログラムの第1回目のテーマがとして「佐渡と疫病」を配信しましたよね。そこで実はコレラがものすごく蔓延して多くの方が亡くなったときにまつられた、通称コレラ地蔵と呼ばれる供養塔がかなり人里離れた山奥にあると知ったんです。
吉田:日本では、江戸江戸後期に江戸で大流行して20万人もの死者を出したという伝染病のコレラは、それ以後、明治期に入っても幾度かの大発生があったそうで、佐渡相川でも明治12年に亡くなった人々を供養するため、供養塔が建立されました。中に石地蔵と供養碑が納められていて、この地蔵が俗にコレラ地蔵と呼ばれています。鉱山都市である相川は、人々の出入りが盛んであったため、伝染病の流行も多かったと推測されていて、もし不幸にして死亡すると、当時の人々は煙によっても伝染すると考えられていたので、普通の火葬場には入れず、獣道を歩いて辿り着くまでに2、3時間の路傍まで運んで野焼きにしたそうです。「虎列刺病死三百七十三人供養塔」と刻まれた石碑が安置されています。
椹木:地元の人はそこへ行ったりもするんですか?
吉田:いや、全然知らなかったです。民俗学者の池田哲夫先生が芸術祭のキーマンでして、椹木さんと佐渡の民話や民族的な部分を研究していく中でも彼が道案内をしてくださることが多く、コレラ地蔵も池田先生が教えてくださって。道中で自分たち島民であっても知らないことを知る機会があって、それがアート作品のテーマになっていくところもある。
椹木:「目一つ」もそうですよね。一つ目の妖怪伝説は柳田國男の本にも出てきますし、全国各地にありますが佐渡のものがかなり重要で。
吉田:2016年に私が「目一つ」という作品を展示したんです。そのときに椹木さんに来ていただいて、それがきっかけで忘れ去られた目一つという妖怪の研究が始まって。今は廃れてしまっていますが、集落の男性だけが御堂に集まって罵り合う奇祭が佐渡にもあって、そこで目一つが御堂を覗くときに追い払う呪文があったらしい。ただ、全て口伝で伝わっている伝統的な行いなので、集落の人がいなくなれば自然と消えてしまう。もしかしたら、そこで何か治められていたものが今は治まってないのではないかという話にもなってくる。これはまだ研究途中ですが、そのオコナイをもう一度復活させたほうがいいんじゃないかとアドバイスをいただいています。

先端的なエネルギーを生みだす佐渡の機運と可能性
椹木:佐渡というと金山銀山とか、たらい舟みたいなステレオタイプなイメージがまっさきに浮かぶかもしれないけれど、近代以降の歴史的事実として、二・二六事件の思想的根幹だった北一輝は佐渡出身です。民俗学者の柳田國男や宮本常一も興味を持って訪れていたり、先駆けて何かを作り出すような精神的な機運があることが少しずつわかってきた。実は僕も知らなかったのだけれど、北一輝の弟、北昤吉が多摩帝国美術学校(現在の多摩美術大学)の創設者として理念を作りに関わった人なんですよね。佐渡がルーツなんて多摩美の職員にも先生にも学生にもたぶんほとんど知られていないと思う。伝統だけでなく、そういうアートや現代美術に繋がってくる部分もあるんだなと。過去の歴史と結びついて、事実そこが強みではあるけれど、それに対するカウンターみたいなのも常にあって、先端的なエネルギーみたいなものを生み出すのではとも思うんです。
吉田:佐渡って、東京から見たときと瀬戸内の島から見たときの印象で全然違って。すごく特異な場所で、悪い意味でいえばどこからも遠く閉ざされているように見えるし、ドヨーンとした雰囲気もある。椹木さんがおっしゃられたように、芸術祭は負のイメージを隠さずに逆に掘り起こして見せていくことで、見つめ直すきっかけを作ることをこれからも続けていかないといけない。
椹木:離島だと地理的に閉ざされているように位置付けられがちですが、海を起点にして考えれば、全く孤立しているわけではなく、どこかへ向かうための停泊地とも捉えられる。特に近代以前、鉄道と道路が交通の手段になる以前は、佐渡が大陸と列島のハブになっていたわけで、物や人の行き来も相当あったはず。今は見えないいけれど記憶を繋げて、痕跡を可視化していくのが、今後の佐渡の芸術祭の一つの方向性なんじゃないかなと。佐渡の芸術祭の大きなテーマとして、「過去と未来の帰港地」という言葉がある。今まさに現在に過去を呼び寄せて未来に向かっていこうとしているところです。かつて瀬戸内と佐渡が海路で繋がっていたことも芸術祭をやらなかったら知らなかったですし。掘れば掘るほど金鉱じゃないですけど、そういう地脈が出てくるのが佐渡なのかもしれない。
吉田:掘りがいがあるとも言えますし、いろいろなものが集まっちゃう場所でもありますよね。
椹木:濃縮されているから、ちょっと強すぎると感じる人もいるかもしれない。でもそこも魅力ですよね。楳図かずおさんにも参加していただいているけれど、『わたしは真悟』の最終局面で真吾が念を送る先が佐渡だったじゃないですが。やはり何かを感じとる場所なんだと思う。作品の設置場所もそういう経緯から生まれましたし。佐渡では、創作や人や思想、日蓮から世阿弥から柳田國男から宮本常一から北一輝から楳図かずおまでいろんなものが続々と繋がる。
吉田:今年は「FRACTAL CAMP」でテリー・ライリーまで繋がりましたね。
椹木:そういう場所は他にはそうないんじゃない(笑)。これは何年に1回開催とか決めているんですか?
吉田:大きく本祭として開催するのは3年に1回で、プロジェクトとしては毎年やっていきます。
椹木:仮にコロナが去ってもまた何が起こるかわからない。本当に先の読めない世の中になったので、何かが起こったときに人との繋がりみたいなものが大事なのだとしたら、この芸術祭がそういうものの伏線にもなっていく気がする。
吉田:一昨年のシンポジウムで、椹木さんが「観光は光を観るって書く」という話をされていたことでハッとして。来た人が単純に作品を見てチェックマークをして帰るという場所じゃなく、光をみんなが観るような禅や祈りに近い感覚というか、そういう場所を今後も目指していきたいなと。
椹木:観光というのは本来、ありがたいものに出合うためのものに近いんじゃないのかな。近代以降はツーリズムとして使われる言葉になったけれど、今芸術祭で求められているのは巡礼的な体験だと思うし、不便なほうが体験の密度が濃くなることもある。そういう意味では、半島や離島、盆地のほうが日本の芸術祭の可能性があるのかもしれないと佐渡で改めて思いました。
プロフィール
椹木 野衣
美術批評家。多摩美術大学教授、同芸術人類学研究所所員。著書に『増補シミュレーショニズム』(ちくま学芸文庫)、『日本・現代・美術』(新潮社)、『反アート入門』『アウトサイダーアート入門』(ともに幻冬舎)、『後美術論』『震美術論』(ともに美術出版社)、『感性は感動しない』(世界思想社)など。さどの島銀河芸術祭アドバイザーも務める。
吉田 モリト
一般社団法人 佐渡国際芸術推進機構 代表理事/ プロデューサー/ 美術家。新潟県佐渡島生。2016年「さどの島銀河芸術祭」を立ち上げ、総合プロデューサーを務める。
Interview&Text:Tomoko Ogawa
